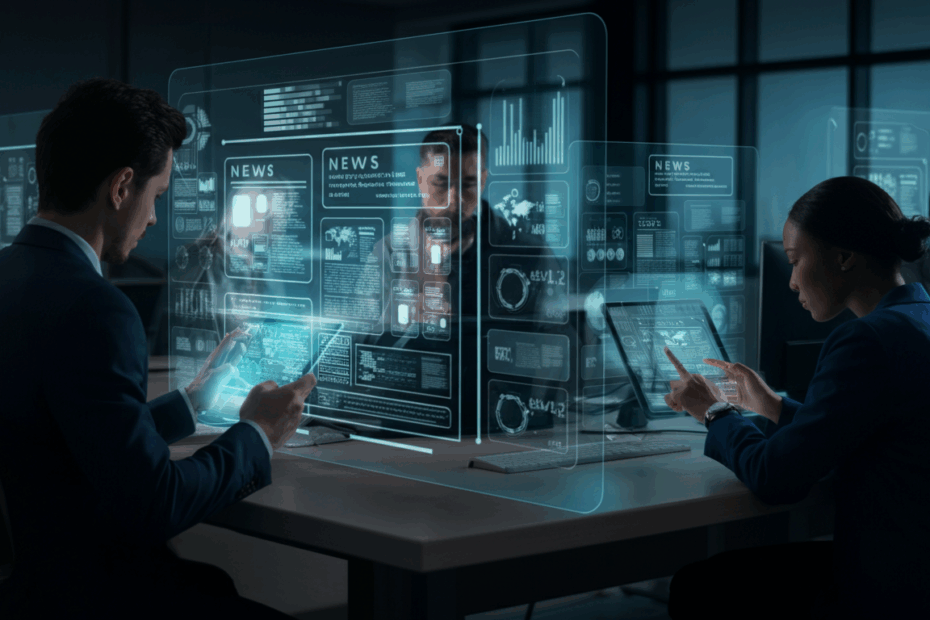AIブームはもう終わり?ニュース業界が直面する「理想と現実」の壁
こんにちは、AI解説ブロガーのジョンです。2023年は「生成AI」の話題で持ちきりでしたね!まるで魔法のように文章や画像を作ってくれるAIに、「未来が来た!」とワクワクした方も多いのではないでしょうか。
でも、最近こんなことを感じませんか?「あれ、AIって思ったよりも万能じゃないかも…?」「どうやって仕事に活かせばいいのか、いまいち分からない…」。そう、大きな期待の波が少し落ち着いて、現実的な課題が見えてくる時期。実は今、多くの業界がそんな「理想と現実」のギャップに直面しています。特に、情報の最前線にいるはずのニュース業界が、まさにその真っ只中にいるようなんです。
今回は、海外のメディア業界向けの記事を参考に、ニュース業界におけるAI活用の「今」と、その可能性について、誰にでも分かるように、やさしく紐解いていきたいと思います。
「AIって、こんなもの?」テクノロジーがたどる「幻滅期」とは
新しいテクノロジーが登場したとき、私たちの期待度は一本調子で上がり続けるわけではありません。実は、ある決まったパターンをたどることが多いと言われています。
コンサルティング会社のガートナーが提唱する「ハイプ・サイクル」という有名なモデルがあるのですが、簡単に言うとこんな感じです。
- 黎明期(れいめいき):新しい技術が登場し、一部で注目され始める。
- 流行期(ピーク):「これはすごい!世界が変わる!」とメディアが大きく取り上げ、期待が最高潮に達する。
- 幻滅期(げんめつき):実際に使ってみると「あれ?意外と使えない…」「問題も多いじゃないか」と、期待が大きかった分、がっかり感が広がる。
- 回復期:幻滅期を乗り越え、「この技術の本当の強みはここだね」「こういう使い方ならうまくいく」と、地に足のついた理解が進む。
- 安定期:技術が社会に定着し、当たり前のように使われるようになる。
元記事によると、今のニュース業界は、まさにこの3番目の「幻滅期」にいるのではないか、と指摘されています。ChatGPTなどの登場で一気に期待が高まったものの、いざ導入しようとすると、コストの問題、正確性の問題、使いこなせる人材がいないなど、様々な壁にぶつかっているのです。
なぜニュース業界は「がっかり」しているの?
ここで一つ、面白い比較があります。GoogleやMeta(旧Facebook)のような巨大テック企業は、もう何年も前からAIをサービスの中核に組み込んでいます。彼らはすでに5番目の「安定期」にいます。検索エンジンの精度を上げたり、あなたにピッタリの広告を表示したり、AIはビジネスの根幹を支えています。
一方、ニュース業界は、これまで「記事を書く」「取材する」といった人間のスキルが中心でした。巨大テック企業のように、膨大なデータを学習させたり、優秀なAIエンジニアを何百人も抱えたりする体力は、なかなかないのが現実です。
つまり、プロの料理人が最新の厨房で腕を振るう(巨大テック企業)のに対し、ニュース業界は「最新のすごいオーブンを買ったけど、使い方がまだよく分からない…」という家庭の料理人のような状況、と考えると分かりやすいかもしれませんね。
じゃあ、AIはニュースのために何ができるの?具体的な4つの可能性
「幻滅期」は、決してネガティブなだけではありません。ここを乗り越えてこそ、本当の意味でAIを使いこなす道が見えてきます。では、具体的にニュース業界でAIはどんな風に役立つのでしょうか?元記事では、大きく4つの可能性が挙げられています。
- 記事づくりの効率アップ:
これは一番イメージしやすいかもしれませんね。例えば、長時間の記者会見の音声を自動で文字に起こしたり、膨大な量の調査レポートを数分で要約したり。記者の人たちが、より創造的で重要な「取材」や「分析」に時間を使えるようになります。 - 読者体験(UX)の向上:
AIを使って、読者一人ひとりに合わせたニュースを届けることができます。「あなたが先日読んだサッカーの記事、面白かったですか?でしたら、こちらの選手のインタビュー記事もおすすめです」といった具合です。これにより、読者はもっとニュースサイトを好きになってくれるかもしれません。 - 新しい収益源の創出:
AIの力を借りて、新しいニュース商品を作ることも考えられます。例えば、特定のテーマ(「環境問題」や「子育て」など)に関する一週間のニュースをAIがまとめて、専門的な解説を加えた有料ニュースレターを作る、なんてことも可能です。 - ビジネス運営の最適化:
これは裏方の話ですが、とても重要です。どのような記事が読まれやすいか、どのタイミングで購読を促すメッセージを送れば効果的かなど、ビジネス面のデータをAIが分析し、会社の経営をサポートします。
このように、AIは単に「記事を自動で書く」だけでなく、ニュースという仕事のあらゆる場面で「頼れるアシスタント」になってくれる可能性を秘めているのです。
成功のカギは「AI推進リーダー」の存在
では、どうすればこの「幻滅期」を抜け出せるのでしょうか。元記事が強調しているのが、「AI推進リーダー」の存在です。
これは、社内に一人(もしくは小さなチーム)、「AIの導入と活用」を専門に担当する人を置く、という考え方です。このリーダーは、記事を作る編集部と、サイトを作る技術部の「橋渡し役」となります。
現場の記者が「こんな作業が大変なんだ…」と抱える悩みを吸い上げ、それを解決できるAIツールを探してきたり、技術チームに開発を依頼したり。逆に、技術チームが「こんな面白いAI技術がありますよ」と提案するのを、現場がどう使えるか具体的に考えたり。そんなコミュニケーションの中心に立つ人がいることで、AI活用は一気に進む、というわけです。
僕自身、このAIの「幻滅期」という考え方は、ニュース業界に限らず、あらゆる分野で起こっていることだと感じます。最初は魔法のように見えたものが、だんだんと身近な「道具」になっていく。その過程で試行錯誤するのは、ごく自然なことなんですよね。
大事なのは、そこで諦めずに「じゃあ、この道具をどう使えば自分たちの仕事がもっと良くなるだろう?」と考え続けること。ニュース業界の挑戦は、私たちにとっても他人事ではないのかもしれません。
この記事は、以下の元記事をもとに筆者の視点でまとめたものです:
Are news companies in the era of unfulfilled potential with
AI?